
コラム
中小企業庁が発表している中小M&Aガイドラインは、後継者不在に悩む中小企業経営者などが参考にしたいガイドラインです。中小企業ならではの事情に配慮しつつM&Aについて解説しています。この記事では、中小M&Aガイドラインの概要と押さえておきたいポイントなどを紹介しています。
8,500名のプロ人材・顧問が登録するプラットフォーム「顧問バンク」。
M&Aに知見やノウハウのある人材、人脈を活用した営業活動の強化、社内の経営課題の解決に最適な人材に直接アプローチ!
→まずは、【公式】顧問バンクにアクセスしてPDFを無料でダウンロード
目次
中小M&Aに用いられる主な手法として、以下の5つが挙げられます。
【M&Aの手法】
それぞれの概要は次の通りです。
株式譲渡は、売り手側の株主が保有している株式を買い手側に譲渡して、対象となる会社の経営権を買い手側に承継させる手法です。売り手側は、株式譲渡の対価として現金を受け取ります。株式譲渡のポイントは、会社組織をそのまま引き継ぐことです。資産・負債のほか、従業員との契約、取引先との契約などは基本的に存続します。
事業譲渡は、売り手側が保有する事業の全部または一部を買い手側に譲渡する手法です。譲渡する事業には、不動産・設備などの資産や負債、知的財産権なども含みます。売り手側は、事業譲渡の対価として現金を受け取ります。事業譲渡のポイントは、株式譲渡よりも手続きが複雑になることです。例えば、労働契約の承継には個別の承諾が必要になります。また、不動産を譲渡する場合は、登記手続きも必要です。
会社分割は、会社法が定める組織再編手続きのひとつです。中小企業庁が発表している資料で、以下のようにまとめられています。
会社の事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割し、他の会社(又は分割に伴い新たに設立する会社)に包括的に承継させる手続である。
引用:中小企業庁財務課「『中小M&Aガイドライン』について」
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200331001/20200331001-3.pdf
一定の要件を満たす場合に、労働契約は引き継がれます。会社分割のポイントは、他の手法に比べると時間がかかることです。会社法で、債権者に異議申立期間(1カ月)を設けることが定められています。
合併も、会社法が定める組織再編手続きのひとつです。売り手側が抱えるすべての権利・義務を買い手側に承継させます。合併により、売り手側の権利・義務は消滅します。すべての権利・義務には、資産・負債・契約などが含まれます。包括承継を基本とするため、労働契約は買い手側企業に引き継がれます。会社分割と同じく、会社法の定めにより債権者に異議申立期間を設けなければならない点には注意が必要です。
業務提携・資本提携は、企業間で業務上の協力を約束する手法です。業務提携は資本の移動を伴わず、資本提携は資本(株式)の移動を伴います。資材の共同調達や商品の共同開発が代表的な例といえるでしょう。中小M&Aの場合、今後の事業承継に向けた取り組みのひとつと考えられています。
中小企業庁は、「中小M&Aガイドライン」を発表しています。中小M&Aガイドラインは、中小企業を対象とするM&Aのガイドラインです。具体的に、どのようなものなのでしょうか。
M&Aは、中小企業の事業承継に重要な役割を果たす手法です。社会的なニーズを受けてM&Aの件数は増加傾向ですが、中小企業経営者の中にはM&Aを躊躇する方もいます。M&Aに関する知見が不足しているため、どのように進めればよいかわからないからです。また、M&A仲介サービスの手数料などがわかりにくい点や、信頼できるM&A支援の判別が難しい点もM&Aを躊躇する原因といえるでしょう。後継者不在に悩む中小企業が、M&Aを躊躇することは望ましいといえません。そこで策定されたのが、中小M&Aガイドラインです。
参考:中小企業庁「2018年版中小企業白書」
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H30/h30/html/b2_6_2_2.html
中小M&Aガイドラインの目的は、中小企業経営者が必要に応じてM&Aを選択できるようにすることです。以上の目的を達成するために、M&Aの基礎知識とM&A仲介サービスにおける手数料の目安を掲載しています。さらに、M&A支援への不信感を払しょくするため、関連機関に対し適切な行動指針も示しています。以上の取り組みなどにより、中小企業経営者にM&Aの理解を促すことを目的としています。
中小M&Aガイドラインは、「後継者不在の中小企業向けの手引き」と「支援機関向けの基本事項」で構成されます。「後継者不在の中小企業向けの手引き」は、M&Aに対する理解を促すため中小M&Aの事例を紹介するとともに、M&Aの進め方や仲介手数料の考え方を掲載しています。基本的なM&Aのプロセスを図解で示している点やM&A仲介会社の選び方、手数料の判断基準を示している点がポイントです。「支援機関向けの基本事項」は、M&A仲介会社や金融機関などへ向けた資料で、支援機関としての基本姿勢や行動指針などを掲載しています。
半年で約3,500万の利益を出した方法とは?
人脈を活用した「新規開拓営業の方法論」についてはコチラをチェック!↓
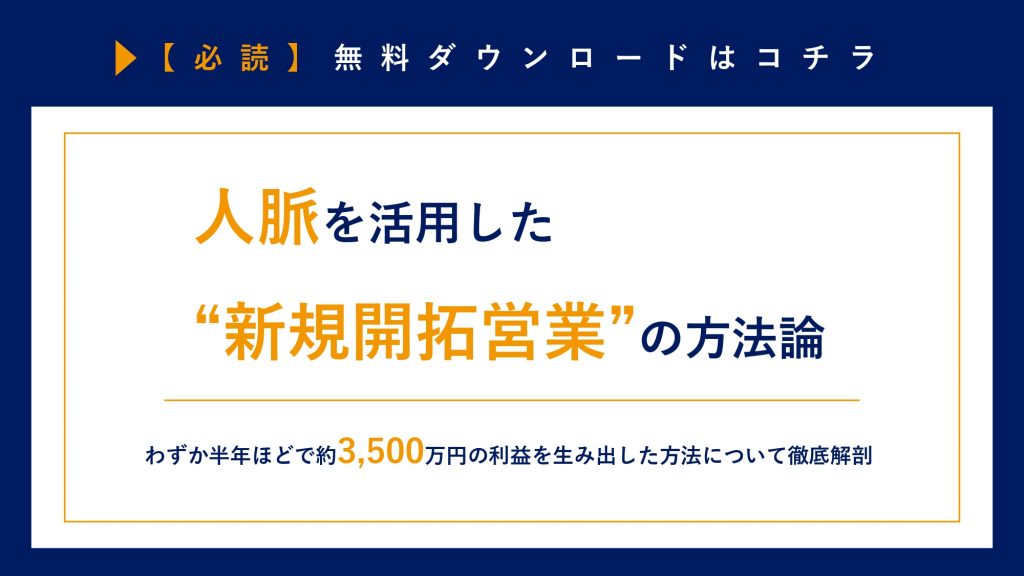
ここからは、中小M&Aガイドラインの「後継者不在の中小企業向けの手引き」について、具体的な内容を紹介します。
この項目では、ガイドラインの意義を説明しています。具体的には、後継者不在に悩む中小企業の特徴を踏まえてM&Aについて説明している点を意義としています。中小M&Aは、大手企業のM&Aとは異なる点が少なくありません。例えば、後継者不在に悩む中小企業の多くは、廃業を回避する手段としてやむなくM&Aを選択しています。したがって、売り手側は、M&Aの知識・経験がほとんどありません。以上の事情に配慮してM&Aについて解説している点が、中小M&Aガイドラインの意義なのです。
この項目では、中小M&Aにおける一般的な中小企業の動き方をフロー図で示すとともに、各工程における主な支援機関を記載しています。例えば、譲り受け側の選定(マッチング)では、M&A専門業者や金融機関、M&Aプラットフォーマー、センターが主な支援機関として挙げられています。中小M&Aの全体像を、一目で理解できる点がポイントです。
急速に普及しつつあるオンラインM&Aプラットフォームについて説明している項目です。具体的には、M&Aプラットフォームの定義や利用における留意点、利用手数料などについて解説しています。例えば、利用手数料では、現在のところ売り手側に手数料は課されないケースが多いと説明されています。
「事業引継ぎ支援センター」は、中小M&Aのマッチング、マッチング後の支援、従業員承継に関する支援、事業承継に関する相談受付を実施している機関(事業継承・引継ぎ支援センター)について説明する項目です。具体的な業務内容や設置場所などが掲載されています。M&Aを検討する際に確認しておきたい項目といえるでしょう。
この項目では、M&A仲介会社・FA(ファイナンシャルアドバイザー)の手数料について解説しています。着手金・月額報酬・中間金・成功報酬で構成されるケースが多いため、これらの概要を説明しています。具体的な事例も示されているため、どれくらいの手数料がかかるかイメージしやすいはずです。
中小M&A実施過程や中小M&A終了後に利用できる相談窓口を掲載している項目です。具体的には、事業継承・引継ぎ支援センターと日本弁護士連合会(ひまわりほっとダイヤル)が掲載されています。
受注率が高い営業手法にはこんな手法もあります。
人脈を活用した「リファラル営業」についてはこちらをチェック!↓
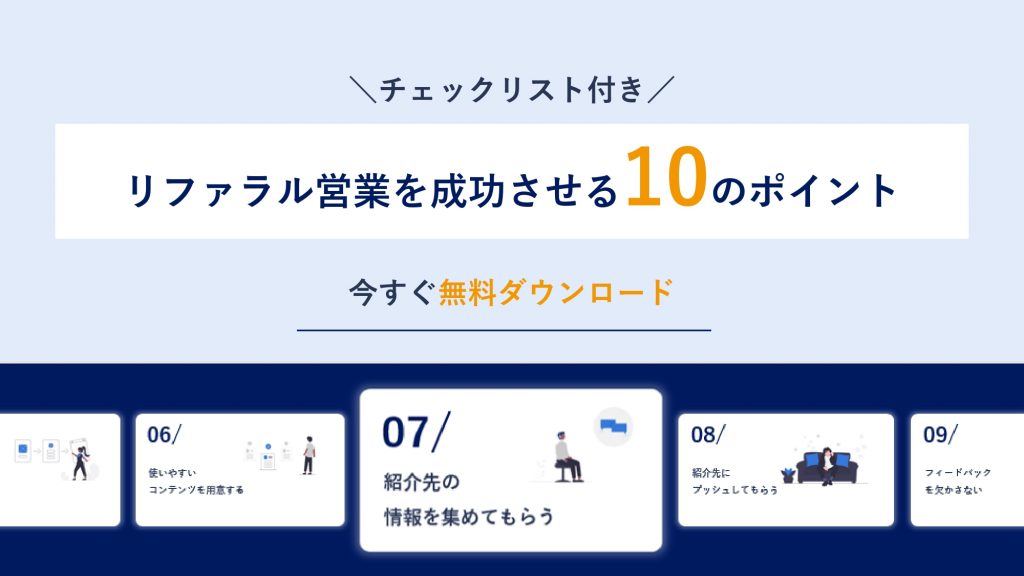
中小企業庁が発表している「中小M&Aガイドライン」は、中小企業経営者が必要に応じてM&Aを選択できるようになることを目的とするM&Aについてのガイドラインです。後継者不在に悩む中小企業に向けたM&Aの手引きと支援機関に向けた基本事項などを掲載しています。
中小企業ならではの事情に配慮しているため、一般的な解説では物足りない点をしっかりと解説している点がポイントです。M&Aを検討している中小企業経営者が参考にしたいガイドラインといえるでしょう。ただし、実際にM&Aを選択すると、専門的な知識も必要になります。中小M&Aガイドラインで不足を感じる場合は、顧問と企業のマッチングサイト「顧問バンク」でM&Aに強い専門家を見つけて相談してみてはいかがでしょうか。
8,500名のプロ人材・顧問が登録するプラットフォーム「顧問バンク」。
M&Aに知見やノウハウのある人材、人脈を活用した営業活動の強化、社内の経営課題の解決に最適な人材に直接アプローチ!
→まずは、【公式】顧問バンクにアクセスしてPDFを無料でダウンロード
御社の課題を顧問で解決してみませんか?
顧問マッチングプラットフォーム
顧問バンク
スポット起用から長期まで、「必要なとき」「必要な人数」
課題にあわせて自由に選べる顧問マッチングサービス。
雇用リスクを抑え
即戦力を活用できる
迅速なマッチングで、
あらゆる課題に対応
中間マージン0円優れた
コストパフォーマンス